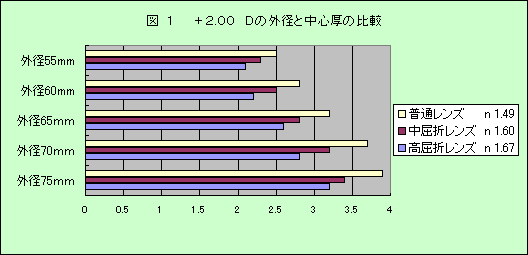
このページは多少、レンズについての知識が必要です。
27 参考資料 1 レンズ外径と中心厚について
一般にレンズの中心の厚みは、レンズの度数、素材の屈折率、 レンズ外径、
レンズ設計(非球面)など で決まってきます。
下記の表は、度数+2.00 D のレンズの、屈折率とレンズ外径に対する中心厚
を示しています。
注 レンズ外径とは、枠入れする前の全てのレンズはまるい円形です。
この枠入れ加工する前のレンズ(uncutlens)の直径を指します。
表の見方
度数+2.00 D のとき高屈折レンズで外径75mm(在庫規格)で製造した場合
中心厚は3.2mmになります。 同じ条件で外径70mmに外径指定して製造
すれば2.8mmにできます。 すなわち凸レンズの場合外径を小さくすれば
厚みを薄くできます。 参照 特注加工につて
次に普通の素材(nd 1.49)を使って外径を60mmに指定して研磨すれば中心厚
は2.8mmとなり、高屈折素材レンズの在庫規格(3.2mm)より薄くなリます。
このように必ずしも高屈折なレンズは薄いとは限りません。
あなたの選んだフレームに必要な、最小レンズ外径を眼鏡店で相談して下さい。
資料 1 数値は計算値です(実測値と異なります)
| 表1 レンズ外径と中心厚の関係 | |||||
| 度数 +2.00 D では | 外径75mmの場合 | 外径70mmの場合 | 外径65mmの場合 | 外径60mmの場合 | 外径55mmの場合 |
| 高屈折レンズ nd 1.67 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
| 中屈折レンズ nd 1.60 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 普通レンズ nd 1.49 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
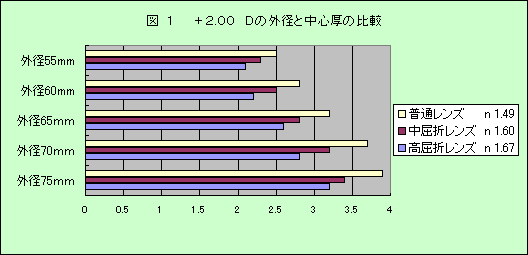
このように同じ度数のメガネでも条件にもよりますが、中心厚2.1mmから3.9mm
まで約2倍近く違ってきます。 (度数が強いほど差が大きくなります)
あるお客様からの質問です。
小さいフレームの場合、外径の大きいレンズなら 一枚のレンズで両眼 (2枚)
作れませんか?
お答え
いくら外径が大きくても一枚のレンズからは一枚(片眼)しか作れません。
当然といえば当然ですが、 なぜか考えてみて下さい。
参考資料 2 レンズ素材の屈折率の判別の仕方について
屈折率の違いによるレンズ厚み比較表(EXCEL.圧縮ファイル)
メガネをつくるとき、どのような特性のレンズを使うか(レンズの種類)を指定して
発注します。 レンズメーカーから送られてきたレンズの袋にはそのレンズの
度数、中心厚、屈折率、非球面、など、さまざまな特性が表記されています。
一方 「レンズにキズが入ったのでレンズを交換して下さい」 と持って来ら
れたお客様のレンズには何の情報も書かれていません。
しかしほとんどの情報は眼鏡店設置の レンズメーター、厚み計、 ベースカーブ
計 などで判断できますが、一番大切な素材の屈折率の測定は店ではできません
(一般に高屈折レンズほど薄くなりますが、上記のように外径指定していた場合は
厚みは屈折率の判断基準にはなりません)
そこで私達は一つの方法として、そのレンズの水中屈折力を測定し空気中の屈折
力との比から屈折率を判断しています。
空気中屈折力÷水中屈折力=3.03 であれば素材の屈折率は1.50です。
空気中屈折力÷水中屈折力=2.32 であれば素材の屈折率は1.60です。
空気中屈折力÷水中屈折力=1.97 であれば素材の屈折率は1.67です。
空気中屈折力÷水中屈折力=1.75 であれば素材の屈折率は1.80です。
図2 簡易グラフ(横軸の通常の度数に対する水中度数の交線が屈折率となります)
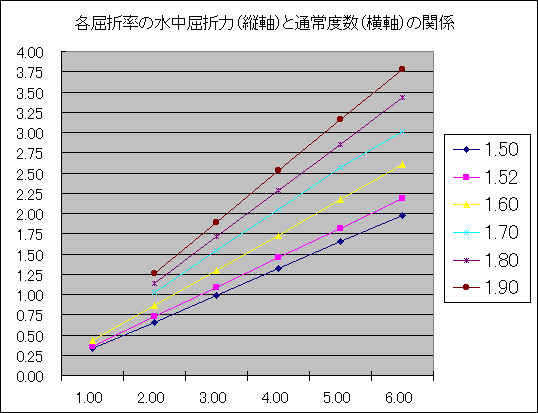
尚 上記 比の値は計算値です 水中度数の測定には測定誤差が生じますので
あくまでも参考値として下さい。